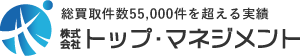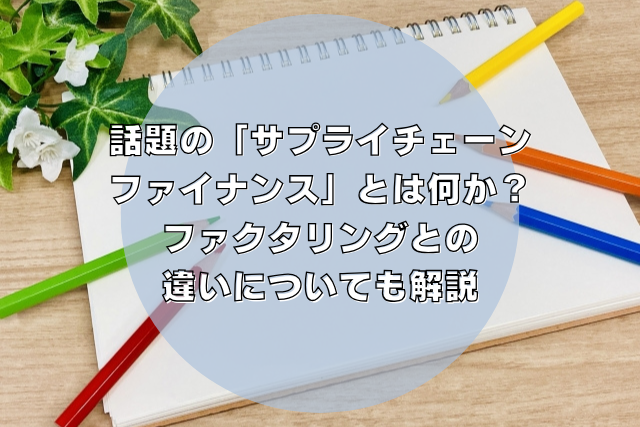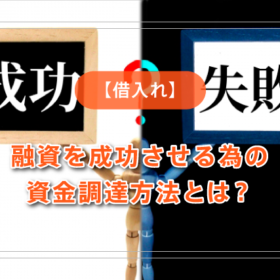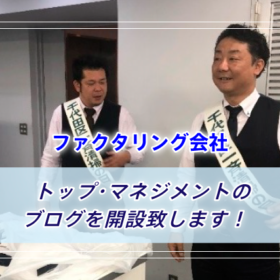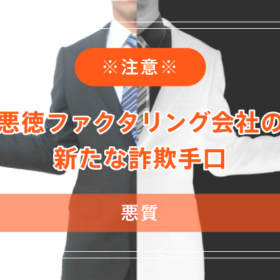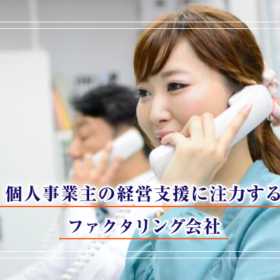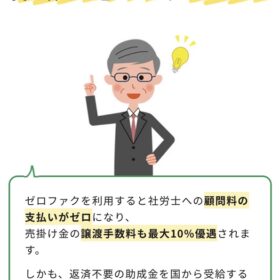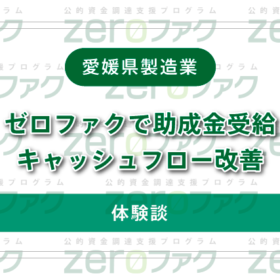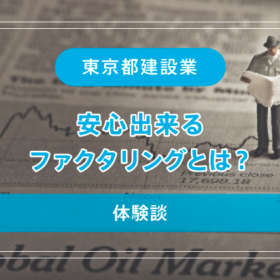みなさまこんにちは。
トップ・マネジメントです。
最近、「サプライチェーンファイナンス」という金融手法がネットニュースなどで取り上げられる機会が増えました。もともとは欧米で普及した金融手法ですが、日本国内でもその導入が進みつつあり、多くの企業が注目しているといわれています。
では、サプライチェーンファイナンスとは具体的にどのようなものであり、なぜ急速に注目度が高まっているのでしょうか。今回は、サプライチェーンファイナンスの仕組みやメリットとデメリット、ファクタリングとの違い、そして将来的な展望などについて解説します。
サプライチェーンファイナンスとは?
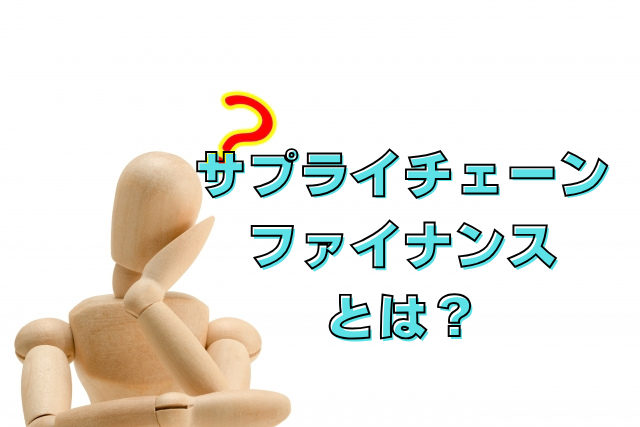
サプライチェーンファイナンスとは、企業が取引先との資金の流れを最適化し、キャッシュフローを円滑にするための金融手法です。
掛取引が一般的である企業間の取引では、納品後に一定の期間を経て支払いが行われることが当たり前。しかし、この期間が長くなるほど仕入先は資金繰りが厳しくなり、経営の安定性を損なう可能性が考えられるものです。
サプライチェーンファイナンスは、金融機関や第三者機関を活用したうえで、こうした資金の流れを改善することを目的としています。
例えば、大手企業が仕入先に対し、より短期間で資金を支払うために金融機関の協力を得ることにより、サプライヤー(商品やサービスを提供する側の企業)が売掛債権を金融機関に売却して早期に資金を調達する仕組みがあります。
サプライチェーンファイナンスの仕組み
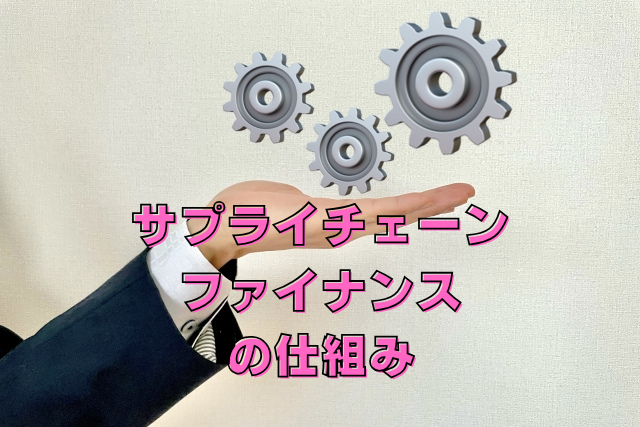
もう少し詳しく、サプライチェーンファイナンスの仕組みをみていきましょう。
サプライチェーンファイナンスは、基本的には買い手企業、サプライヤー、金融機関の三者によって成り立っています。取引の流れを詳しくみていきましょう。
まず、買い手企業がサプライヤーから商品やサービスを仕入れた後、通常の支払いサイクルでは数十日から数ヶ月の支払い期間が発生します。この間、サプライヤーは資金を回収できず、運転資金の確保が難しくなることがあります。
こうしたケースで活用できるのが、サプライチェーンファイナンスです。
まずは、買い手企業が金融機関に対して、自社が承認した支払予定の売掛債権を登録。金融機関はこの情報をもとに、サプライヤーが早期に資金を受け取れるように資金提供を行います。さらに、サプライヤーは金融機関から資金を受け取り、買い手企業が当初の支払い期限に金融機関へ支払う形となります。
これにより、サプライヤーは待機期間を短縮して早期に資金を確保することが可能になるわけです。
この仕組みによって、サプライヤーは資金繰りの安定を図ることができるとともに、買い手企業も取引先の経営安定を支援することができるため、サプライチェーン全体の信頼性を向上させることができます。
また、金融機関は手数料や利息を収益源とし、リスクを管理しながら企業に資金提供を行います。
サプライチェーンファイナンスは普及するのか?
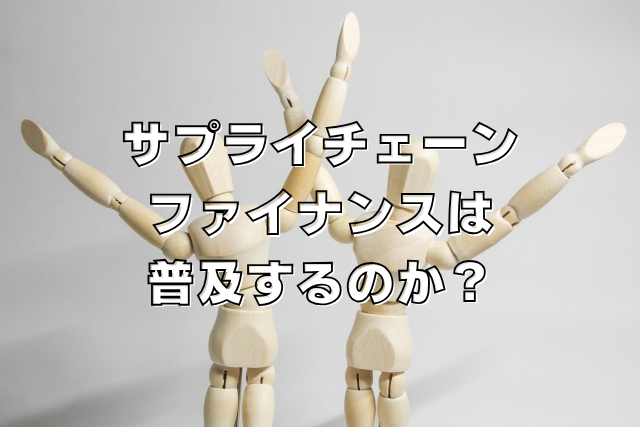
結論を言えば、サプライチェーンファイナンスはこれから先、ビジネスの世界に広く普及していくと考えられます。
その理由の一つには、中小企業の資金繰りの課題が挙げられます。商品やサービスを納品しても代金の支払いを受けるまでに時間がかかる中小企業は多く、支払いを受けるまでの間の運転資金確保に窮するケースは珍しくありません。
銀行融資では審査が厳しく、信用力が十分でない企業は資金調達手段に苦労することが多いものですが、サプライチェーンファイナンスであれば、大企業の信用力を活用できるため、低コストでの資金調達が可能になります。
また、デジタル技術の進化も普及を後押しすることでしょう。
ブロックチェーン技術を活用することにより、売掛債権の取引履歴を透明に管理でき、金融機関も迅速に与信判断ができるようになります。さらには、AIを用いた信用評価システムが発展すれば、リアルタイムでの審査が可能になることから、より多くの企業がサプライチェーンファイナンスを利用しやすくなります。
こうした背景から、サプライチェーンファイナンスは、企業が安定した取引を続けるための重要な手段として、今後さらに普及していくでしょう。
サプライチェーンファイナンスとファクタリングの違い
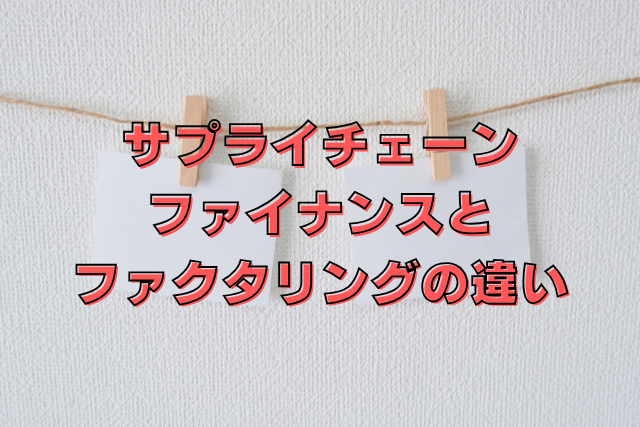
サプライチェーンファイナンスとファクタリングは、どちらも企業の資金繰りを支援する金融手法であり、売掛債権を活用する点では共通しています。
サプライチェーンファイナンスは、主に大企業やそのサプライヤーが利用し、取引の信頼関係をベースに資金を流動化する仕組みです。そのメリットは、取引関係を維持しながら、低コストで資金調達が可能になる点。ただし、大企業との取引が前提となるため、中小企業が単独で利用するのは難しい場合があります。
対してファクタリングは特定の売掛債権を現金化するための手法であり、信用力に関係なく資金調達ができる点が特徴です。企業規模を問わないうえに、取引先にも依存せずに資金化できる柔軟な手段。ただし、サービスによっては利用手数料が高くなるケースがあり、資金調達コストの負担が増える可能性があります。
このように、両者は似た役割を果たしながらも、それぞれ異なる強みと課題を持っています。企業は自社の状況に応じて、サプライチェーンファイナンスとファクタリングを適切に使い分ける判断が求められるのではないでしょうか。
サプライチェーンファイナンスとファクタリングは共存可能なのか?
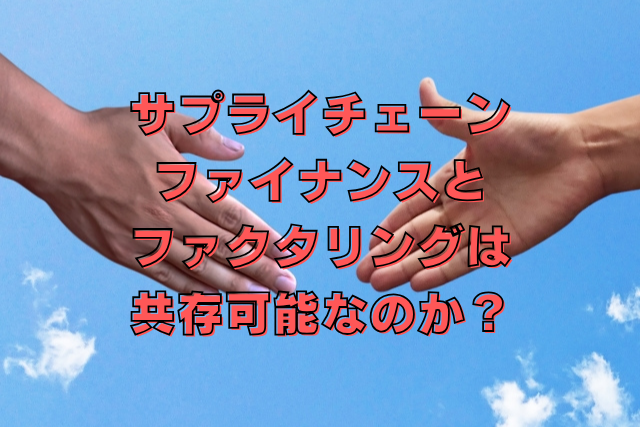
例えば、サプライヤーが特定の大企業との長期取引を持っている場合は、サプライチェーンファイナンスを活用することで安定した資金調達が可能になります。
一方で、急な資金ニーズが発生した場合や、取引相手がサプライチェーンファイナンスの仕組みを導入していない場合には、ファクタリングを利用することで即座に資金調達を行うことができます。
また先にも述べた通り、ファクタリングは主に中小企業向けに有効であり、信用力の低い企業でも売掛債権を活用して資金調達が可能です。
サプライチェーンファイナンスの枠組みに入ることが難しい企業が資金調達を行う際には、ファクタリングが有力な選択肢となります。
このように、サプライチェーンファイナンスとファクタリングは異なる金融手法ですが、共存させることは十分に可能です。それぞれの特性を理解することによって、企業はより柔軟な資金調達が可能になると考えられます。