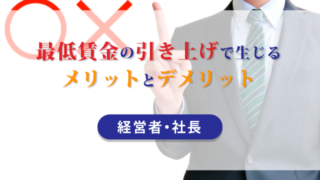会社を経営するうえで、欠かせない施策のひとつといえば法人税の節税対策です。継続的な事業を行うためにも、できる限りの節税を行なって資金を節約したいところ。
法人の節税方法には、本社家賃の年払い契約や社用車の購入などいくつか挙げられますが、今回ご紹介する方法は「役員社宅制度」です。
まだ起業したて、もしくはこれから起業を考えている人からすれば「一般的な社宅」と「役員社宅」の違いがどこにあるのか、疑問が生じるかもしれません。
では、「役員社宅制度」とはどのような制度なのでしょうか。その定義や特徴について解説していきます。
目次
役員社宅制度とは?

会社が家賃を一部負担することにより一般の従業員が割安で入居できる住宅が「社宅」と言われるのに対し、「役員社宅」はその名の通り会社の役員が利用する住宅を指します。
したがって、役員社宅制度とは会社名義で契約した住宅を役員に貸し出し、役員に家賃の一部を負担してもらう制度ということになります。
役員社宅制度のメリット

会社負担の家賃分は全額を損額計上可
役員社宅制度の導入によって得られる最大のメリットが、その高い節税効果。
具体的には、会社名義の賃貸住宅に役員が入居することにより、会社が負担する家賃分を全額損金として経費計上できるようになります。
ひとつ例を挙げてみましょう。
会社が家賃20万円の物件を賃貸契約したとします。そのうちの50%を役員が負担し、残りの50%を会社側が負担する場合、年間120万円を全額損金として計上できるということになります。
言うまでもなく、その120万円は会社の利益から差し引くことが可能になるため、結果として法人税の節約につながるというわけです。
社会保険料の負担額が軽減される
もうひとつのメリットは、会社側が負担する社会保険料額が軽減されることです。
社会保険料の支払いについては、従業員と会社が折半して負担することはすでにご存知でしょう。
「標準月額報酬」と呼ばれる基準をもとに算出されるため、授業員の給与が上がるほど、会社側の負担額は大きくなり、反対に下がれば社会保険料の負担額は下がることになります。
この原則は役員に対しても同じように適用されます。
役員が受け取る報酬は「役員報酬」と呼ばれますが、役員社宅の家賃は役員報酬から差し引かれますので、自動的に役員報酬の額も引き下がることになります。
したがって、役員報酬が引き下がる分だけ、会社の社会保険料額を軽減することができるようになるのです。
役員の手取り減額を抑えられる
役員社宅の家賃は会社と役員の折半で支払われます。
もしも、役員が個人で住居を賃貸契約した場合には、その家賃を全額負担しなければなりません。役員報酬が60万円で家賃が20万円であれば、まるまる20万円を支払う必要があり、単純計算でも手取りは40万円。
一方、役員社宅に入居し、たとえば50%ずつの家賃設定がされれば、支払いは会社と半々。つまり役員は、家賃を10万円に抑えられ、手取りは50万円になります。
割安で質の高い物件に入居できるのはもちろん、必然的に役員報酬の手取り減額を抑えるメリットが生まれます。
これらのように、役員住宅制度の導入は会社にとっては節税や社会保険料の減額、役員にとっては家賃の支払いにかかる手取りの減額を抑えるなど、双方にメリットがあるといえます。
役員社宅に求められる要件

では、どのような住宅であれば役員社宅として認められるのでしょうか。
要件1 法人名義による賃貸契約
ひとつめは、法人名義で賃貸契約した物件であること。
仮に、役員個人が物件のオーナーと賃貸契約を交わし、家賃の一部を会社が負担しても、その負担分は「住宅手当」にしかなりません。
つまり、役員個人名義で契約を交わしても、節税どころか逆に課税対象となってしまうのです。
役員社宅として認められ、家賃分を全額損額計上するためには、必ず法人名義で契約する必要があります。
要件2 家賃の一部を役員が負担する
2つ目の要件は、家賃の一部を役員が負担するという点。
家賃をなるべく多く損金として計上したいと考え、全額を会社が負担しても残念ながら、その分をまるごと利益から差し引くことはできません。この場合は、「経費」ではなく「給与」としてみなされるため、会社側が負担した家賃分は「役員報酬」の一部。役員の個人名義で賃貸契約を交わしたときと同じように、課税対象にあたります。
だからといって、自由に家賃の負担額を設定できるかといえば、それも不可能。
会社の負担分、役員の負担分は、それぞれ国税庁が定める役員社宅についての規定に従って設定しなければなりません。
規定についての詳細は、のちほどの項で詳しく解説します。
要件3 家賃の支払い者は会社であること
3つめは、家賃の支払い者が会社であることです。
たとえば、家賃20万円の物件を役員社宅にして50%ずつを負担する場合、物件のオーナーに対して会社が10万円を支払っておき、その後に役員が残りの10万円を支払うといった流れを導入することは認められません。
役員社宅として認められるためには、オーナーへの支払いに関して必ず全額を会社側が支払う必要があります。そのため、役員の負担分については、役員報酬から天引きする形が原則です。
役員社宅の家賃負担額に関する規定

さて、前項で触れた通り、役員社宅の家賃負担額は国税庁が定める規定にしたがって決定しなければなりません。
その規定が、床面積に応じて「小規模な社宅」「小規模以外の社宅」「豪華社宅」の3タイプに分けるもの。入居する住宅はいずれかのタイプに区別され、さらに、役員が負担する家賃はそれぞれの条件に応じた計算方法によって算出されます。
小規模な社宅
小規模な社宅にあたるのは、法定耐用年数が30年以下の場合は床面積が132㎡以下、30年以上の場合は99㎡以下の住宅です。
そして、以下の3つの計算式で求められる金額の合計が役員の負担する家賃分となります。
・ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
・(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
小規模以外の社宅
上記の小規模な住宅に該当しない住宅は、小規模以下の社宅と定義されます。また、小規模以外の役員社宅の場合は、自社所有の社宅か他社の所有物かで、算出方法が変わります。
自社所有の社宅の場合
以下の2つの計算式で求められる合計額の12分の1が役員の負担する家賃分となります。
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
他者の所有物の場合
一方、他者の所有物に入居する場合は、会社が支払う家賃の50%の金額と、その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%の金額、いずれか多い方を支払います。
豪華社宅
さらに、床面積が240㎡を超える住宅、または設備や物件の価格等を考慮したうえで、上記2タイプよりも高級な建物であると判断された住宅は豪華社宅にあたります。
役員が入居する住宅が豪華社宅に該当した場合は、役員社宅とは認められず節税効果を得ることができません。
また、床面積が240㎡以下であっても、プールや役員個人の好みがはっきりと反映された住宅は、豪華社宅に該当する場合もあります。
役員社宅制度導入にあたっての注意点

家賃負担額の計算や比較は入念に
役員社宅における役員の家賃額は、上記3つのタイプに応じた要件や計算式で求めるのが原則ですが、実は豪華社宅以外の住居であれば、負担額を大まかに50%と設定しても厳しい追及を受けることはほとんどありません。
これは、そもそも固定資産税の課税標準額を求めるのが困難なケースが多いため。
したがって、難しいことは考慮に入れずに負担額を50%に設定してしまえば良いと考えがちです。
ただし、最近では固定資産税の課税標準額を簡単に確認できる制度があり、この制度を利用することによって正しい負担額の計算も容易く行うことが可能です。
つまり、正しく算出した金額によっては50%の設定よりも多くの金額を損金として計上することができ、会社としてもより高い節税効果を得られる場合もあるというわけです。
損金として計上できるのは原則として家賃のみ
生活にあたっては様々な費用が発生しますが、損金の対象になるのは原則として家賃のみです。水道光熱費やネット回線費、駐車場の利用費などについては課税対象となりますので注意が必要です。
ただし、入居に際して必要な準備費用。たとえば賃貸契約における仲介手数料や敷金、引っ越し費用などについては全額を損金として計上可能です。
また、管理費や火災保険料など、一部を損金計上できる費用もあります。
社内規定に役員社宅制度について明記する
新たに役員社宅制度を導入するにあたっては、必ず社内規定にその旨を明記しておく必要があります。
これは、役員社宅についての定義やルールを明確化し、それに従った制度が施行されていなければ、税務調査が行われた場合などに問題視される場合があるため。曖昧な家賃設定など、杜撰な取り決めのままでいると追徴課税といった事態も招きかねません。
役員社宅制度を導入する場合は、忘れずに社内規定に追記をし、適切な制度施行を心がけましょう。
まとめ

今回は、「役員社宅制度」について解説しました。
役員社宅制度は、会社名義で契約した住宅を役員に貸し出し、役員に家賃の一部を負担してもらう制度です。
会社が負担する家賃分を全額損金として計上できるほか、社会保険料の負担額も抑えられるなど、会社側にとってのメリットがありますので、未導入の会社は、節税対策として導入されてみてはいかがでしょうか。
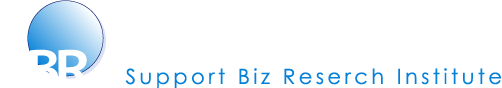
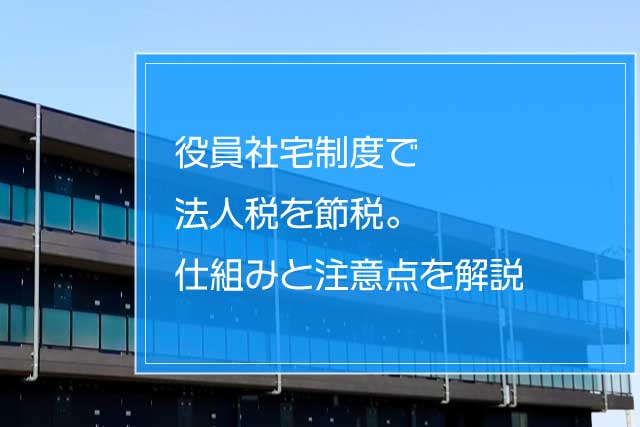

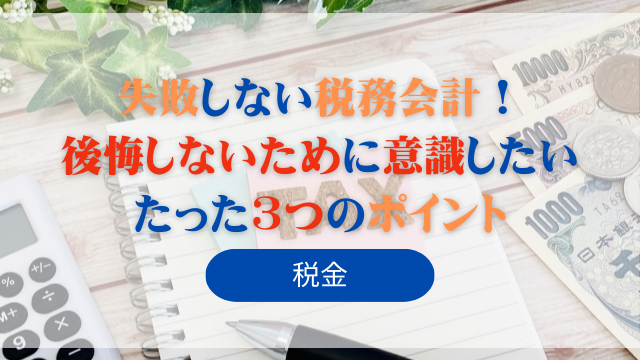
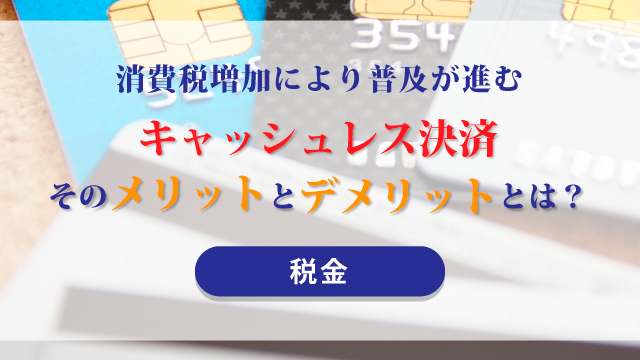

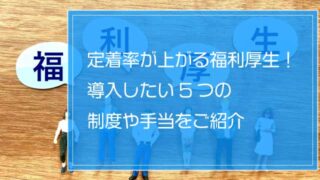
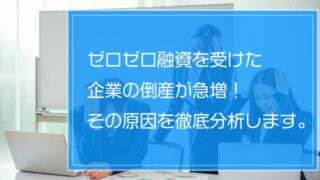
 ランキング1位
ランキング1位
 ランキング2位
ランキング2位
 ランキング3位
ランキング3位