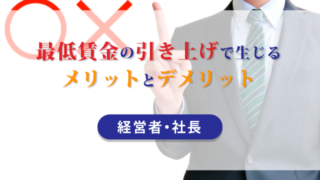会社員が、会社を退職する際に受け取る退職金。退職金は、退職する会社員や役員に対して給与の後払いや老後の資産といった意味合いから支給されるお金であり、勤務した会社の規模や、条件を満たすことによって数千万円もの大きな金額を受け取れる場合もあります。
しかし、原則として支給された全額が手元に残るということはほぼありません。
その理由としては、退職金に対しても通常の給与や賞与と同じように税金が課せられるためです。
退職金に課せられる税金については、「退職所得控除額」という控除制度に応じて税額が変動することになっていますが、2024年に予定されている税制改正によって、同制度が見直され、現在よりも税負担が増す人が増加する可能性が示されています。
では、2024年以降、退職金課税にどのような変化が予想されているのでしょうか。現状における制度についても併せて解説していきます。
退職金の課税対象額を算出する現状の方法

退職金の課税に関して、まず大きなポイントなるのが「退職所得控除」です。
「退職所得控除」とは、勤続年数に応じて控除額を算出する制度であり、勤続年数が長くなるほど税負担が軽くなります。
具体的には、勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、21年以上の場合は70万円が非課税です。
現状の「退職所得控除」は以下のように計算します。
勤続年数 20年以下 控除額 40万円×勤続年数
勤続年数 20年以上 控除額 800万円+70万円(勤続年数−20年)
たとえば、20年間勤務したのであれば、40万円×20年で800万円が非課税。30年間勤務した場合は、40万円×20年で800万円、さらに70万円×10年で700万円、合計で1,500万円までが非課税となるわけです。
退職金を受け取った際は、この非課税額を超えた金額が課税対象になります。
ただし非課税額を超えたからといって、そのすべての金額が課税対象になるわけではなく、さらに「1/2課税」と「分離課税」という制度が適用されます。
「1/2課税」は、課税対象額が半分になる制度です。
退職金から「退職所得控除」で差し引き、非課税額を超えた金額が100万円となった場合は、その半分にあたる50万円が課税対象になります。
そして「分離課税」は、退職金以外の収入があったとしても、その収入とは別に税額を算出するという制度です。
2021年の税制改正で導入された「短期退職手当等」

上記3つの制度のほか、2021年の税制改正によって導入されたのが「短期退職手当等」です。
この制度の対象になるのは、勤続年数が5年以下で退職金を受け取る人。対象者は、「退職所得控除」を差し引いた金額が300万円を超えると、その金額に「1/2課税」を適用することができなくなったのです。
2024年の税制改正で見直しが予想される「退職所得控除」

このように現状の退職金課税には、上記の「退職所得控除」、「1/2課税」、「分離課税」、それに「短期退職手当等」の4つの制度を用いて税額を算出することになっています。
このうち、2024年の税制改正によって変化がもたらされると予想されているのが「退職所得控除」です。
先にも述べたとおり、現状の「退職所得控除」では勤続年数が20年以下であれば1年間に40万円、21年以上になると20年までは40万円、それ以降は70万円が差し引きされるわけですが、これが勤続年数を問わず一律の金額にあらためられると考えられています。
その意図としては、「労働者の転職をより円滑にする」ことが挙げられます。
もちろん勤続年数にもよりますが、退職金は給与や賞与にくらべて大きな金額を受け取れる可能性があります。
したがって、なるべく高額の退職金を受け取り、さらに課税額を抑えようと、長く同じ会社に在籍したいと考える会社員は少なくありません。
これに対し、現在のような段差のある「退職所得控除」の金額が一律になれば、会社員は長く在籍することによって退職金は増えても、課税の面においては大きな利点を感じられなくなり、退職金制度に縛られることなく転職を検討に入れられるようになると期待されるということになります。
労働者の転職が活発になれば、特定の産業や業種への人材集中を避け、人手不足の解消に期待できます。また企業としても優秀な人材確保の促進や流出を避けようと労働者にとって有利な条件の整備に注力する可能性も高まるはずです。
ただし、2024年の税制改正によって仮に「退職所得控除」にメスが入っても、すぐに算定方法が変更されることは考えにくいものです。人生設計や事業活動など、労働者と企業の双方に悪影響が出ないよう、段階的に変更されていくのではないでしょうか。
まとめ

今回は、現状における退職金課税の仕組みと2024年の税制改正によって変更が予想される点について解説しました。
現時点で有力視されているのは、「退職所得控除」の金額一律化。その意図としては、労働者の転職を円滑化することにあると考えられます。
納税する労働者個人だけでなく、企業としても退職金制度に対してどのように向き合うかを検討するべきなのかもしれません。
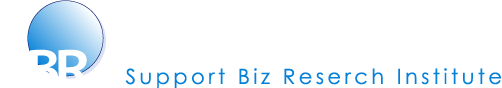



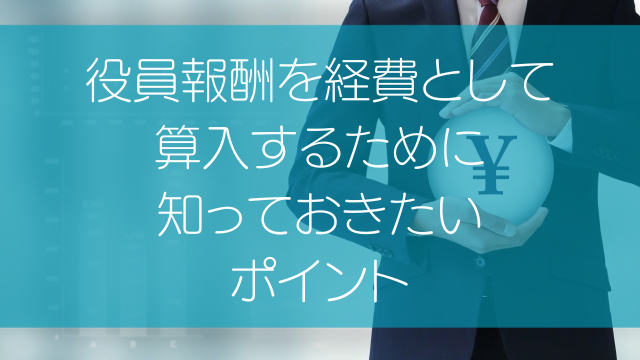

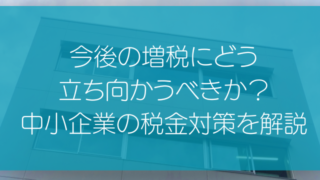

 ランキング1位
ランキング1位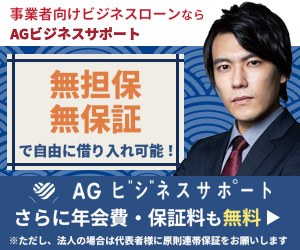
 ランキング2位
ランキング2位
 ランキング3位
ランキング3位